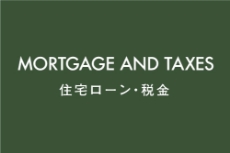重層長屋とは?建築基準法による定義を解説
2021.02.22暮らし
長屋と聞くと、江戸時代から続く古い木造の建物を思い浮かべる人もいるかと思います。
今回は、重層長屋の特徴について詳しく説明していきます。
重層長屋とは?
重層長屋とは、上下に重なった形状の建物のことです。
玄関は1階部分にありますが、1階と2階が別の住戸で、間取りが異なります。
間取りが異なることから、独身者や世帯持ちなど入居者のニーズに対応しやすい物件です。
建築基準法では、特殊建築物に該当しないため、共同住宅よりも規制がゆるいです。
オーナーとしては、「住戸の面積が広くなるため、家賃を高くできる」「共有部分の管理費を削ることができる」「建築基準法や消防法の規制が緩和される」などのメリットがあります。
重層長屋の5つの特徴
重層長屋には、以下の特徴があります。
・供給が少ない
・各住戸の面積が広い
・建築が難しい土地
・共有部分がない
・各住戸の独立性が高い
供給が少ない
重層長屋は、マンションやアパートと比べ、供給量が少ないです。
平成25年の総務省データによると、居住世帯のある住宅は約5,210万戸で、そのうち長屋は129万戸となっており、全体の2%ほどしかありません。
参考資料:平成25年住宅・土地統計調査(確報集計)結果の概要
そのため、入居者がすぐに決まりやすい傾向があり、オーナーにとっては空室を避けることができます。
各住戸の面積が広い
重層長屋は、各住戸の面積が広いです。
賃貸の場合は、階段や廊下などのスペースが必要になるため、全体的に部屋の面積が狭くなる傾向になります。
重層長屋は、共有のスペースが不要になるため、その分、部屋の面積を広くできます。
特殊な地形でも建築できる
重層長屋は、狭小地や変形地など建築が難しい土地でもうまく活用することができます。
マンションやアパートなどの共有住宅は、特殊建築物に該当するため、避難や防火などに関する厳しい規定があります。
そのため、一定の土地面積がないと建設することができません。
しかし、重層長屋は特殊建築物には該当しないため、共有住宅ほど規定が厳しくありません。
狭い土地や形がいびつな土地でも建設できます。
共有部分がない
重層長屋は、廊下やエントランスなどの共有部がありません。
そのため、近隣住民とも顔を合わせることがありません。
また、共有のスペースがないことでメンテナンスにかかる費用を抑えることができます。
長屋のオーナーと居住者の双方にかかる負担が軽減できます。
各住戸の独立性が高い
重層長屋は独立性が高いです。
共同住宅(マンションやアパート)の場合は、上下左右に部屋が連なっています。
防音性が高くない限り、生活音や話し声に悩まさせるケースも多いです。
一方、重層長屋の場合は、住戸が上下に位置しているのみなので、マンションやアパートと比べると独立しています。
2階に住んでいれば、騒音問題に悩まされることも少なく、住み心地がよくなります。
重層長屋と棟割長屋との違い
棟割長屋(むねわりながや)とは、住戸が界壁で区切られた建築物を指します。
界壁とは、住戸の間を区切る壁のことです。
重層長屋を含め一般的な長屋は横方向に区切られていますが、棟割長屋は、建物の真ん中にも壁を作り、両隣だけでなく背合わせにも住戸が作られています。
そのため、多くの世帯が入居することができます。
おわりに
重層長屋とは、1階部分に玄関があり、1階と2階で住戸が異なる建築物を指します。
建築基準法では、特殊建築物に該当しないため、法的規制が比較的ゆるいです。
1階と2階で間取りが違うため、単身者や世帯持ちなど、個人のニーズにあった間取りを提供できます。
狭小地や変形地に建てやすく、建築コストも抑えることができるため、長屋の中でも注目を集めている建物です。
長屋についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
関連記事:長屋とは?建築基準法による定義を解説
最新記事 by SCHOOL BUSリノベーションジャーナル編集部 (全て見る)
- 戸建リノベーションの事例をご紹介!後悔しないためのポイントとは? - 2025年5月24日
- リノベーションの際に考えておきたい住宅の耐震性について - 2025年5月23日
- 東京でのリノベーションはいくらかかるの?価格や相場をご紹介 - 2025年5月23日
- 【2025年版】中古マンションのおしゃれなリノベーション22選 - 2025年4月30日
- リノベーションでできるカビ・湿気対策について - 2025年4月30日